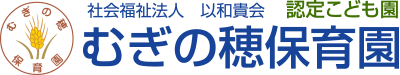乳児期の子どもも一人の人格として大切な存在であり、
その精神と身体の発達はその後の人生のどの時期よりもめざましいものです。
園では保育者との信頼関係を大切にし、個々の成長のリズムに合わせた、
ゆったりとした保育環境を大切にしています。
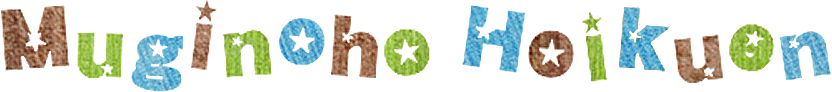
子どもたちの活動


子どもの主体性を大切に
日常生活の作業は、子どもたちにとって、とても興味深い活動です。
例えばガラスを拭く、床を掃くといった活動も、自ら選び、
楽しんで行うことで創造力や集中力が養われます。
当園では、このような子どもの主体性を尊重し、
自分のリズムで納得いくまで繰り返し活動できる
「自由な環境」を整えています。
日常生活の作業は、子どもたちにとって、とても興味深い活動です。
例えばガラスを拭く、床を掃くといった活動も、自ら選び、
楽しんで行うことで創造力や集中力が養われます。
当園では、このような子どもの主体性を尊重し、
自分のリズムで納得いくまで繰り返し活動できる
「自由な環境」を整えています。

実生活の活かせる経験を
教具はできるだけ実物で具体的な物を使うようにしています。
(例えば実際に小さなナイフでバナナを切ったり、ドライバー を
使ってネジをまわしたり)疑似体験ではなく、実生活に合った
経験を積み重ね、依存から自立へと自分の生活を成長させる
ことを目的とした活動を行います。
教具はできるだけ実物で具体的な物を使うようにしています。
(例えば実際に小さなナイフでバナナを切ったり、ドライバー を
使ってネジをまわしたり)疑似体験ではなく、実生活に合った
経験を積み重ね、依存から自立へと自分の生活を成長させる
ことを目的とした活動を行います。

【教具のこだわり】
●子どもが扱いやすいサイズであること
●慎重に扱うことを学ぶべるように、本物(ガラスや陶器など)であること
●色や形が美しく思わずやってみたくなるものであること
●清潔に保つことができ、子どもが汚れに気付けるものであること
●子どもが扱いやすいサイズであること
●慎重に扱うことを学ぶべるように、本物(ガラスや陶器など)であること
●色や形が美しく思わずやってみたくなるものであること
●清潔に保つことができ、子どもが汚れに気付けるものであること


あらゆる面の発達が著しいこの時期、整えられた環境の中で精一杯活動すると、
子どもたちは満足し、心身ともに伸びやかに成長していきます。
そして自分自身の成長は、さらに他への思いやりへと発展していくのです。
子どもたちは満足し、心身ともに伸びやかに成長していきます。
そして自分自身の成長は、さらに他への思いやりへと発展していくのです。
日常生活の練習
日常生活の練習は全ての教育の基本であり、教育の全ての要素を含んでいると言えます。
お片づけやおそうじ、洗濯やアイロンがけなどの日常生活の練習を通じて 快適で秩序だった生活を送る習慣を身につけ、生活を依存から自立へと導きます。 感覚教育
子どもは『触覚』『視覚』『聴覚』『臭覚』『味覚』の五感を使って さまざまなことを 分類、比較、秩序づけて喜びます。感覚を磨く最適なこの時期に、 比較することを基本とした感覚教具や具体物に触れる活動によって 感覚を使い洗練させ、ものを考える方法を身につけます。 言語教育
ことばに対する敏感性はすでに胎児期から始まり、人の声、特に自分に対する ことばに反応します。また、3〜6歳の子どもは、環境の中にある文字に対して とても敏感です。
絵カード、文字カード、砂文字板など、発達段階に適した 教具を使い 『話す』・『読む』・『書く』活動を通じて語彙を豊かにし、 さらに文法や文章構成へと発展させていきます。
日常生活の練習は全ての教育の基本であり、教育の全ての要素を含んでいると言えます。
お片づけやおそうじ、洗濯やアイロンがけなどの日常生活の練習を通じて 快適で秩序だった生活を送る習慣を身につけ、生活を依存から自立へと導きます。 感覚教育
子どもは『触覚』『視覚』『聴覚』『臭覚』『味覚』の五感を使って さまざまなことを 分類、比較、秩序づけて喜びます。感覚を磨く最適なこの時期に、 比較することを基本とした感覚教具や具体物に触れる活動によって 感覚を使い洗練させ、ものを考える方法を身につけます。 言語教育
ことばに対する敏感性はすでに胎児期から始まり、人の声、特に自分に対する ことばに反応します。また、3〜6歳の子どもは、環境の中にある文字に対して とても敏感です。
絵カード、文字カード、砂文字板など、発達段階に適した 教具を使い 『話す』・『読む』・『書く』活動を通じて語彙を豊かにし、 さらに文法や文章構成へと発展させていきます。




数教育
子どもは年齢の数の理解ができるといわれます。
大きい、小さい、多い、少ないなど比較し対応していくことで 数的関心が高まります。 抽象的、論理的な力を要求される 「数教育」では、 特に具体物(算数棒、ビーズなど)を用いて 量を体感させることから始め、系統化された多くの教具に よって 細かいステップを踏みながら、抽象へ移行します。
数量概念の基礎から十進法、加減乗除へと子どもを 無理なく導きます。 文化教育
歴史、地理、生物、道徳(宗教)、音楽、体育、美術など 多岐にわたり、それらを体系的に学ぶのではなく、 身近な事物にふれたり、観察しながら文化を獲得する態度を 養い、生命の神秘や芸術に関する興味の幅を広げます。
子どもは年齢の数の理解ができるといわれます。
大きい、小さい、多い、少ないなど比較し対応していくことで 数的関心が高まります。 抽象的、論理的な力を要求される 「数教育」では、 特に具体物(算数棒、ビーズなど)を用いて 量を体感させることから始め、系統化された多くの教具に よって 細かいステップを踏みながら、抽象へ移行します。
数量概念の基礎から十進法、加減乗除へと子どもを 無理なく導きます。 文化教育
歴史、地理、生物、道徳(宗教)、音楽、体育、美術など 多岐にわたり、それらを体系的に学ぶのではなく、 身近な事物にふれたり、観察しながら文化を獲得する態度を 養い、生命の神秘や芸術に関する興味の幅を広げます。